 会誌-「ザラスMCPG 諸英伝」 会誌-「ザラスMCPG 諸英伝」
|
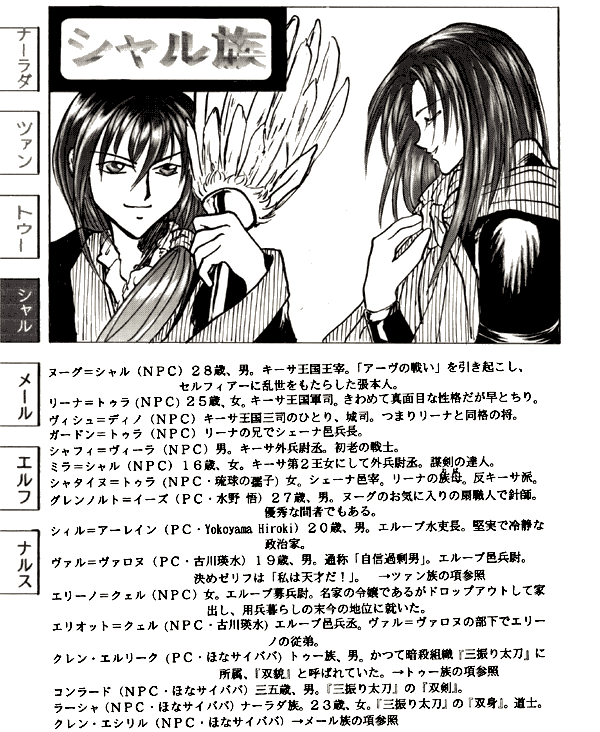
「……そうか、ウォウル邑宰が亡くなったか」 軍司から手渡された書簡を見やって、ヌーグ=シャルは左手の扇を止め、机の上に投げ出した。 「確かな情報か、これは……と、確かめるまでもなかったな」 ヌーグは、このキーサ王国の最高権力者、王宰である。この位に就いて六年目、つまり、「セルフィアー全土」という思考法を五種の民すペてに呼び起こしたあの事変の発案者であり、実行者であり、実戦指揮官でもあった。あの事変を起こしてすぐの頃は、驚きの声ばかりが先行して何ら芳しい反応が見られなかった。そのような中で、非公式ではあったが、すぐさま書簡をよこしてきたのがウォウルの邑宰であった。 「この度の儀、まことに壮挙と心得ている。四百年の永きにわたる平和は、我々に富と繁栄ではなく、停滞と閉塞をもたらした。邑という狭い世界を打ち砕くためには、貴公のごとき手段をもってする他はないであろう。私は既に老兵ゆえ、これから事を起こすことはできないが、次の若い世代に期待したい……」 ヌーグは、このセルフィアーに乱世をもたらそうとしている。それがどういうことなのか、本当に理解していたのは、ウォウル邑宰ただ一人であったといってもよい。すでにして賢才の評価を得た先輩からの言だけあって、ヌーグは大いに力づけられた。 そのウォウル邑宰が亡くなった。一つの時代が、確かに終わったのだ。 ……という実感を噛みしめているヌーグに遠慮して、軍司は黙っていたが、その時間があまりに長いので、口を開いた。 「王宰殿、もう一つ重大な報告がございます」 「どのくらい重大だ? 今の訃報と比しては?」 「こちらの方が重大です。セルフィアー全土を揺るがすほど」 ヌーグは机上の羽扇を拾い上げ、椅子に深く座した。白い羽根の塊が、ちょうど顔の下半面くらいを隠している。 「聞かせてくれ」 「そのウォウル邑宰の後継者が、ウォウル王を称しました」 ヌーグは身を乗り出した。口許を覆って表情を隠しているが、目が何よりも雄弁に驚きと好奇の表情を示している。 「後継者とは誰だ。邑宰──先邑宰の子はまだ幼いのだろう?」 「一四歳といいますから、それほど幼いとも言えないでしょう。まあ、一邑の主となるには若すぎますけれど」 「一四か。うちの王族の初陣より早いじゃないか。そんな奴が、邑宰となり、王を称したのか……」 セルフィアーは確かに変わりつつある。 能力がなくとも年さえとっていれば何とかなったような時代は終わり、能力があればどんなに幼くとも表舞台で働ける世の中になるのだ。ヌーグは面に静かに風を送った。 「しかし、それが臣たちに承認されたのか? 先邑宰はつねづね、群臣が頭が固い、と嘆いていらしたが」 「そこですよ」 軍司は初邑議の模様を語り聞かせた。ヌーグは扇を置いて膝を打った。 「今邑宰は、仲々の演技者だな。倡優としての技倆もなければ、これからの世は渡って行かれまい。それに一四歳にしてあの兵吏長にも勝る剣の使い手か。面白いことになりそうだな」 「使者を送りますか?」 「まあ、待て」 扇を取ってばたばたと扇ぐ。こうやって頭を冷やしてから策を練るのが、ヌーグの癖である。 「使者は出そう。だが、王号を名乗った事への承認では拙い」 「では、王号は認めないのですか」 「そうとは言っていない。ウォウルのナーラダ家といえば、独立戦争の英雄の血筋、しかも四百年もあの大きな城邑を治めてきた。その点では我がシャル家と変わりないのだから……」 「では認めるのですね」 「軍司、少し黙っていてくれ、貴女は結論が早すぎる」 ヌーグは苦い顔をした。そしてまた扇ぐ。 「認めてもよい。だが、まだ時期が早い。認めるのはその邑宰の……名は何といったか」 「ナーラダ・ヴィレクです」 「そのヴィレクという少年の人物と実力を見きわめてからだ」 「分かりました。では、何と使者を出すのです?」 ヌーグは沈黙し、せわしなく左手の扇を動かした。 (邑宰就位の祝辞……だけでは弱いな。なぜ王位即位を祝わぬのかと問われて否定してしまえばその後を取り繕うのが難しくなる。何か付随するものが必要か……) 「軍司、貴女はまだ独身だったな」 「はい、……でも、ナーラダから婿を取れだなんて、そんな……」 軍司は慌てた。ヌーグは首を横に振った。 「何も将来のために誼みを結んでおこうというのではない。夫探しを名目に向こうの有力な男性、ついでに女性についても、詳しい情報を掴んできて欲しいのだ」 「では、私はただのネタですか」 少々憮然とする軍司を、ヌーグはひらひらと扇いだ。 「気に入った男がいれば遠慮なく貰ってこい。同じ五種の民ではないか。……それと、守備範囲外だろうが、ウォウル邑宰の人物もしっかり見てこいよ。これが一番重大だからな」 軍司は、落ちつきがないと思われないように気をつけながら、ウォウルの城邑を見漬した。カノールのように、外観の美しさを求めてはいない。だが居住性となると、或いはこちらの方が勝っているかもしれなかった。民の表情は、明るくはない。英雄が死んで、まだ若い子が立った。しかも王などと言う耳慣れない位を称している。その意味の重大さが分からなくとも、何かが起こるという予感は、この民たちの中にもあるのだろう。 碧い城壁の無効に山が見える。その山容は、キーサのように急峻ではない。穏やかな山、穏やかな湖面、穏やかな空。こんな国で乱を起こしたら、反発を受けるのは当然だという気もする。 (でも、私たちがたまたま良い季節に来ただけかもしれないわね) そして、私たちがたまたま平和な時代に生まれついただけ、という考え方もできるのだ。おそらく、セルフィアーで最後の……。 この時代のウォウルには、まだ後世のもののような内城は出現していない。商店街の中央部が、そのまま官庁街となり、王居となっている。 先触れはしてあった。軍司たちはすぐに王の間に通された。 王の間、といっても邑宰の公室そのままである。何ら手を加えられてはいない。変わったのは名称だけだ。ナーラダ・ヴィレクという少年は、本気で「王」となる気があるのだろうか? 少なくとも、虚栄心からというわけではないようだ。 静かに扉が開いて、一人の少年と壮年の男が入ってきた。軍司は深く頭を下げて礼をしたが、跪きはしない。彼を格上とは見なしていないからだ。 「ウォウル王、ナーラダ・ヴィレクです。以後、お見知りおきください」 少年は実に鄭重に言った。へりくだっていると言ってもよい。 「キーサ王国軍司、リーナ=トゥラです。キーサ王国の正式な使者として参りました」 リーナは名乗り、そして少年をしげしげと観察してしまった。 (何と可憐な……) 少年なのだろう、とリーナは心中呟かざるをえなかった。透き通るようにつややかな白い肌、黒絹のようなみずみずしいまっすぐな髪、描いたような細く形のよい眉、みがいた翡翠石を埋め込んだかと思わせるような大きくよく光る瞳、小さいがふっくらとした唇、そのような風貌もさることながら、一つ一つの動作がいかにも幼い。唇から流れ出る声も、変声期前特有の高い声だが、甲高さはなかった。むしろやわらかく、甘やかで、脳味噌と耳がとろけてしまうのではないかと思うほどだ。 「して、ご用の向きは?」 ヴィレクは単刀直入に言った。リーナははっと我に返った。 「先邑宰の弔問と、ヴィレク殿の邑宰位への即位の祝賀、です」 ヌーグの悪い癖で、次の手を思いつくと前の手はきれいさっぱり忘れてしまうきらいがある。が先邑宰の弔問こそが重大事ではないのか、とリーナは道々思っていた。独断ではあるが、これはヌーグの過失を補う形でのものだから権限の内だろう。 「そうですか……」 呟いて、ヴィレクはにっこりと笑った。無邪気な笑みだ。子供っぽい、いかにも朗らかな。 「父の葬儀はすでに済んでおります。のちほど、墓前にご案内しましょう。それから、祝賀の件ですが……」 笑みを絶やさぬまま、しばらく沈思する。その間、瞳が何回かリーナを見つめた。一点の曇りもない緑の視線が、自分の眼孔から脳の中までを覗き込んでいるような、そんな気がして、リーナは知らず、全身の毛穴が縮むような寒気を感じた。決して、鋭くはない。穏やかな表情だ。だが、その穏やかさが恐ろしい。 「ウォウル邑宰位への即位の祝賀、ですね。分かりました。……貴女には何も訊きませんよ」 くすくすと笑う。さりげなくつけ加えた最後の一言の意味は、 (こちらの意はすべて知っている、ということか) リーナの背に冷汗が流れた。 ヌーグはわざわざ軍司の公室を訪ねてきて首尾を訊いた。 「夫探しの件に関しては、これはと思うような人は見あたりませんでした。それから情勢の方ですが、ヴィレク王の一族……旧邑宰家の者たちの挙動が怪しいですね。例の叔母の兵吏長ルーシは落ち込んで自宅に閉じこもっているようですけれど、その他の者たちが間違いなく動きます」 「それを乗り越えられるかが、今邑宰の命運の分かれ道だな」 ヌーグは楽しそうに言った。リーナは渋い表情をした。 「もう、勝敗は見えてますけどね」 「どういうことだ、軍司?」 ヌーグはぱたぱたとリーナを扇ぐ。リーナは上下する鬱陶しい前髪を押さえて大きく息をつく。 「ヴィレク王は、一言で言うと神のような人物ですよ。……もう、二度と見たくないです」 「仲々の美少年だと、貴女の部下が言っていたぞ」 「ええ、それは全く同感ですよ。ですけど……」 瞼を閉じると、今でもくっきりと浮かんでくる。あの、可憐な、愛らしい笑顔が。 「天敵ってやつですね。二度とウォウルには行きませんよっ」 「分かった分かった」 ヌーグは羽扇の先でリーナの肩をとんとんと叩いた。 「王位への祝賀の時には、この自分が自ら出向こう」 窓へ歩み寄る。向こうの方に見えるセルファニア湖。カノールから見えるのは南湖と俗称される、セルファニア湖でも対岸の見えるような狭い一部分であるが、この湖面は北湖の端、ウォウル城下の港まで続いている。 その、ウォウルにいるという美貌の少年。 自分の起こした乱を、さらに全土に広げようとしている者。 「面白い……」 ヌーグはさも満足げに呟くと、羽扇の柄を二、三度叩いた。 |
「シェーナ邑宰シャタイヌ=トゥラが、何やらおかしな動きをしているようですね」 リーナが王宰の室に報告書を持ってきた。シャタイヌ=トゥラは彼女の族母にあたる。報告書にあるのはシェーナが使者を送ったとされる邑の名であった。アーヴ、シュダなどはキーサの勢力下の邑の中でも外周に位置する中邑だが、中にはディン、アーレといった大邑の名も連ねられている。 「しかしこれが全部賛同するかな」 ヌーグは扇の根本を何度も親指でなぞっている。 「軍司、どう思う?」 「可能性というなら、全部が敵に回る可能性は高いでしょうね」 「やはりその前に先手を打とうか……いや」 ヌーグは扇を握りなおし、額に風を送った。頭を冷やす。こうしてからでないと、ヌーグは決断を下さない。 「どうしますか?」 ぱたぱた。二呼吸ほどおいて、ヌーグは頷いた。 「よし、軍を出そう。外兵と、募兵の半分を連れていけ」 「目的は?」 軍司は立ち上がりながら訊く。 「威嚇、だ。だが状況によっては戦ってよい」 「どのくらいまで勝ってよろしいので?」 負けることは念頭にない。というより、軍司は負けるくらいなら初めから交戦しないのだ。 「そうだな、シェーナをまるはだかにできる程度、だ。城攻めはするな。シェーナの周囲の、オードとかディテとかいうような小邑は占領してこい。シェーナ軍が出てきたらつぶせ」 「……要するに、無理をしなければ何やってもいいと、そういうことですね」 「キーサ軍です!」 その報が入ったとき、シェーナ邑宰は雷に撃たれたように硬直した。ややあって、呟くように言う。 「……やられた。速すぎる。各邑からの返事のまだ四に一つも届かぬうちに……!」 「間違いないのか」 邑宰丞が念を押すと、外吏長は商いた。 「残念ながら。……萌葉色の地に×字の弧は、キーサの両道紋に間違いありません。その数一万二千」 「……多いな。勝てぬ」 シェーナ司祭は首を振った。丞に言う。 「和を乞え。どうせ帥は軍司のリーナだろう。奴なら無為に攻めてきたりはせぬ。和を乞い、膝を屈して時機を待つのだ」 ヌーグが仕事の手を休め、一服やっていると、しのびやかなノックの音がした。そっと入ってきたのはひげを顔中に生やした男である。本来ならば、こんな所に入ってきてよい人間ではない。グレンノルト=イーズ、ヌーグの気に入りの扇職人である。 「ちょうどいま休憩中だ。まあ、そこに座れ」 「毎度どうも。……で、そいつの具合はいかがです?」 「いい具合だな。これは前作を凌ぐよ、保障していい。この柄の長さといい、握り具合といい、風の指向性といい、重くもなく軽くもなく、こんなに手になじむのはお前しか作れんだろう」 「光栄なお言葉で。ところで、扇以外で、何か私に出来ることはないでしょうかね?」 「そうだな。シェーナに行ってもらおうか。内情とは言わぬまでも、様子を知らせてくれるとありがたい」 「分かりました」 そして、またそっと扉の外に消えていった。 |
エルーブ山脈の麓にある邑の中で、エルーブはとりわけて大きな邑である。山脈のうちエルーブ付近だけには銅が産出する。最近はアヴァダでも採れるようになったが、やはりエルーブの銅といえば良質の代名詞である。 ただ惜しむらくはエルーブは交通の便があまり良くない。大消費地である北方の邑へと銅を運ぶためには、陸路で行くなら山脈を越えなければならないし、かといって水路で運ぼうとすれば、川に着くまでが大変である。 エルーブの東に位置するホング湖の畔の木を切り倒し、そこに一つの邑が建造されようとしていた。 「どうだ」 シィル=アーレインは、現場監督者の工部令に声をかけた。 「順調です。もうじき庫吏長様もいらっしゃいますよ」 「庫吏か……」 シィルは少し眉をひそめた。庫吏長はシィルが様々な開発を始めたことをあまりこころよくは思っていないようであるが、それは役目柄当然のことであった。庫吏は財物の管理がその任、開発がうまくいけば財物は増加するが、とりあえずその前に底をつく可能性の方が高そうである。どうやって説得しようかと考えていると、その本人が姿を現した。 「水吏長殿」 「私から出向こうと思っていたのですが」 とりあえず相手が何か言い出す前に機先を制しておく。 「フィーブと同盟しようかと考えております」 いきなりそんな話題を振ったので、庫吏長は呆気にとられた。シィルは構わず続ける。 「つまりですな、水利を便する為には金がかかる。この港邑の建設にしろ、私の考える南邑の建設にしろ、莫大な費用はエルーブ一邑の庫吏では賄いきれない。庫吏長殿のご懸念はそこかと思いますが、その費用を軽減するためには、同盟邑をつくってそこに出させるのが一番よい。そして同盟を結ぶためにはその邑と我が邑とが何らかの利益を共にしていなくてはなりません。フィーブもここに港ができれば大いに交易が振るうでしょう。そう、外吏に進言しました」 一気に言い切ってしまう。相槌を打つ隙を与えない。庫吏長は目を白黒させていたが、 「つ、つまりは、金は思ったほど出さないで済むということか」 と結論づけた。 「さようです」 庫吏長が去ってしまうと、工部令はシィルに問いかけた。 「港邑の建設がこれであることは存じておりますが、南邑の建設とはいかなる事ですか」 「ああ、まだ貴公は存じなかったか」 シィルは頷いて話し始めた。 「我が邑では夏の短い期間しか作物がとれぬ。それは仕方のないことかもしれない。だが、星薬会の者やパールヴァティの神官なら、それを何とかする方法を知っているかも知れない。だから、私は思ったのだ。春先から晩秋、雪のない間ずっと収穫できる穀物を知っている者、育てられる者を集め、収穫が出来るまでは我が邑で生活を保障し、銅以外による第二のエルーブを作ろうと」 「なるほど、庫吏長様がご機嫌ななめであったのは、そのことが主原因だったのですね。この港ではなく」 「なるほど、そういうことなら同盟を結んでも良いですよ」 フィーブの外吏長はあっさりと言った。 「いいのですか、邑宰殿などに相談しなくても」 あまりにも簡単に決まったので、エルーブの外吏は思わず聞き返してしまった。外吏長は笑った。 「東のレディアとホーズ、二つの大邑が戦争を始めたのです。わがフィーブとしては巻き込まれるのは避けたい。しかしそれだと交易を主にあちらに頼っていた我々は干されてしまいます。するといずれかにつかねばならない。いかがいたそうかと相談していたところ。あなたがたの提案はまさに渡りに船、というわけなのです。その港邑建設費については半分といわず、七割、いや八割出してもいい。それでも我々は大いに助かりますのでね」 六年前の事変の時、真っ先に反キーサの兵を挙げたのはファナであった。ためにその後追随して兵を挙げた諸邑から堆され、「反キーサ王国連盟」の盟主となった。しかし瞬く間にヌーグの反間工作にあい、主導権争いが起きてエルーブを中心とする南部連盟とファナの北部連盟に分かれ、南部が北部に勝利して決着がついた。ゆえにエルーブはファナを初めとする周辺の多くの邑から恨みを買っている。先月、シェーナが反キーサ大同盟を起こそうとしたときも、エルーブにはお声がかからなかった。もっとも、すぐにヌーグにつぶされたが。 エルーブ邑兵尉ヴァル=ヴァロヌは二百人ばかりの兵に装備と四週間の時間を与え、猛特訓をさせた。そしてすっかり精鋭部隊が完成すると、 「これより邑外での訓練に移る。目的地はプーツァ」 と言う。ざわめきが走った。プーツァはエルーブに次いで南にある邑だが、他の周辺の邑がどちらかといえば反キーサ派であるのにもかかわらずキーサと仲が良い。エルーブは一応反キーサ派に属すると思われている。プーツァに行くとは戦争を仕掛けることではないのか。 「兵吏長の命もなしにプーツァに出かけたのか !?」 エルーブ募兵尉エリーノ=クェルは間の報告を聞いて呆れ果てた。 「いやいや、命を与えてないわけではないぞ」 その独言に背後から答える声があった。 「へ、兵吏長、聞いていらっしゃったんですか?」 「ああ。可愛い妹の様子が変だと聞いたんで、やってきたのさ」 「ふん、なにがかわいい妹だ。助平兄貴め、のぞき見してたな」 すぐ本性が出る。兵吏長は苦笑した。 「それはそうとだ。ヴァルには一応命を下したことはあるぞ。『お前の軍をもっと役立つようにして、実戦で役立つところを見せろ』とな。俺は実戦の時役立つようにしろの意で言ったのだが、実戦をやって試せの意味だと取ったんだろうな、奴は」 「わざと曲解したんだろ。奴はそう言う奴だ」 エリーノは決めつけた。 「それにせよ、負ける戦はしないだろうからな……」 あらかじめ城壁内に間者を忍ばせておき、外の攻撃に呼応して邑内の各所に火をつけさせ、食糧を奪った後自分たちの攻撃に対するキーサ王国の無策ぶりを挙げつらい、エルーブについた方がよいと書いた高札を置いて去る。 「完璧な作戦の完璧な遂行。……私は天才だ!」 「何てことをしてくれたのだ」 庫吏長は兵吏長とヴァルを前に頭を抱えた。 「港邑の建設、南邑の建設だけでも金がかかるのに、この上戦争も始めるというのか !? そんな金がどこにあるというのだ。私は規定予算以上は絶対に兵吏には回さないからな!」 「勝てばよい」 ヴァルは昂然と言った。 「勝てば財宝も糧食も手に入る。そちらから回してもらう必要はなかろう」 「勝てば、な。負けたらどうなるかは、考えてもいないわけか」 「考える必要もあるまい」 「……勝手にしろ」 「プーツァから救援要請?」 ヌーグは軍司と顔を見合わせた。 「エルーブが攻め込んで……? シェーナと謀ったんでしょうか」 ぱたぱた。 「いや、グレンからの連絡もないし、多分違うだろう。単なる突発事態と思っていいんじゃないか」 「しかし、この高札は放っておけませんね」 一に日く、キーサ王国は六年前に挙兵したにも関わらず、未だシャル族居住地域どころかキーサ高原すら制圧できていない。 二に日く、我々の行動を阻止できぬほど友邑への援助は薄い。 三に日く、そのためにみすみす食糧を焼かせ、家を焼かせ、人を焼かせた。云々。 「勝手なことを……!」 軍司は机を叩いて怒ったが、 「まあまあ、落ちつけ軍司」 ぱたぱた。軍司の顔をあおぐ。 「これは怒らせるのが目的だ。逆上しては向こうの思うつぼだぞ」 「では、兵は出さないのですか」 ころっと意見が変わる。ヌーグは首を振った。 「大兵を送ればこちらががら空きになる、それだけのことだ。少しの兵と、有能な指揮官を送ろう。……軍司、行ってくれるな」 「──御意」 |
エルーブ邑兵尉ヴァル=ヴァロヌ、通称「自信過剰男」の独断専行により、シィルの考えていたプランは大きく狂わされた。 シィルは、別に親キーサ派というわけではない。いずれキーサとは戦わねばならないとは思っている。だが、今戦っても勝てないのは目に見えている。 ヴァルには、大局が見えていない。シィルはそう思う。それとも、大局を見て戦うという思考自体、彼には備わっていないのだろうか。確かに、将としては優秀だろう。少数の兵による奇襲の見事さという点においては、おそらく当代一であろう。そのことははからずも証明された。だが、それが何だというのだ。戦術レベルでの勝利が戦略・政略レベルでの勝利に必ずしも結びつかないのは兵法の素人でもわかる。無理にでも結びつけるつもりか? だとすると、 (まさに、自信過剰だな……) 彼のような男が出てくるのも、時流というものなのだろうか。 冷静、沈着、頭の回転も悪くない。ただ、彼には根本的なものが欠けている気がする。戦いを求め、戦いでの勝利を求めるあまり、国としての成長、民の安寧、そういったものをまったく忘れているのではないか。 民なくして、国は存在し得ない。軍もまた然り。 国を富ませ、技術を根付かせ、人を増やし、兵を増やし、それから時を味方につけて。 この邑を、『エルーブ帝国』にするために── (最悪の場合は、彼を処分することも考えねば……) 「プーツァに攻め込んだそうですね」 朝議で邑宰は開口一番そう言った。兵吏長は頭を下げた。 「申し訳ありません。私の監督が行き届きませず……」 「全くだ」 庫吏長が吐き捨てた。 「私は規定予算以上は絶対に兵更には回さないぞ!」 「予算のことを言っているのではありませんよ、庫吏長。これが我がエルーブの利になるのであれば、私としては出費を惜しもうとは思いません。まず庫吏長、それ以上に言うことはありますか」 「もちろん、あります」 庫吏長は憤然として言った。 「戦など金を食うだけです。それに、我がエルーブは、人口ではキーサの半分、穀物の収量は年に五分の一と、規模の点で大きく劣っています。その上カノールはセルファニア湖に面し、年中交易が可能です。消耗戦になれば全く勝ち目はありません」 「道理ですね」 水吏長シィル=アーレインは同意して頷いた。 「私が考えるに、現在キーサに対し戦を起こすことには、四つの不利があります」 指を折る。 一つめは、距離の不利。エルーブの近くには邑がほとんど存在しない。大軍が移動できる道がないのだ。実質、キーサ軍よりも到着までの日数は多くかかるだろう。 二つには、庫吏長の言ったとおり、財の不利。エルーブの財を支えるのは現在、銅のみである。つかってもつかっても湯水のように出てくる豊かな財源がなければいけない。 三つめは、土地の不利。エルーブは、食糧という条件に関してはセルフィアーでも最悪といっていい。土質の大部分は鉱毒をふくむため食糧が生産できず殆どを他邑から輸入している。 四つめは、時の不利。反キーサ同盟の分裂により、キーサは労せずして他邑のカを弱めることに成功した。カをたくわえ、時を待つべきだろう。 また、今のエルーブには『正義』がない。 「以上、四つの点を抜きにしましても、今度の邑兵尉のおこないました行為は『野盗』と大差なく、まったくもって最悪の事態であると思われます」 邑議でそんなことになっているとは知らぬヴァル=ヴァロヌは、着々とキーサ軍を迎え討つ作戦に精を出していた。 「なかなか援軍が来ないな」 「キーサのですか?」 ヴァルの副将、エリオット=クェルが訊ねた。 「いや、我が軍のだ。作戦が成功したと、お前の従姉に知らせてやったから、もうそろそろ来る頃だと思っていたのだが……」 「キーサ軍はもうそろそろ到着するようですよ。あちらに土煙が見えます」 エリオットの指さす方を眺める。なるほど、軍が来るようだ。 「エリオット、兵数はどのくらいだと思う?」 「千、かそこらではないでしょうか」 「合格だ。まあ、あれくらいなら今の兵力でもなんとか勝てるな」 「二百で、ですか? 邑兵尉、それはいくらなんでも無謀すぎますよ。引き揚げましょうよ」 「いや、私に一計がある。案ずるな。そもそも、戦争というのは敵の裏をかくことを本質とする。敵将リーナは我々のことを全く知らないが、私はリーナがどういう将であるのかを知っている。また、私は敵の兵数を知っているが、敵は私の兵数を知らない。勝つためにはこれだけの条件が揃っていれば十分だ。いいか、こういう計だ。『三重夜襲の計』というのだが……」 リーナに与えられた兵力は千。しかしカノールとプーツァの間には、キーサに良からぬ感情を持っている邑がたくさんある。今度の出兵の目的は挑発に報いること、それに兵糧の輸送だ。他の邑にかまっているわけにはいかない。 そこで考えたのは、平服を着て旅人に偽装し、目的地で合流することであった。作戦の性質上気心の知れていた者の方がいいだろうということで、六年前のアーヴ攻略時からの兵がほとんどである。部下には元衛兵で外兵尉丞の老兵シャフイ=ヴィーラ、王女で同じく外兵尉丞のミラ=シャル、それに謀ニーゼ=フェノといった実力派を従えている。 キーサ軍が陣を築き始めたところで、何やら騒ぎが起こった。 「軍司殿に会わせて下さい」 などと誰かが言っていて、それに対し兵が怪しい奴、と尋問を行っているらしい。 リーナが行ってみると、一人の男が取り押さえられていた。平服を着た、シャル族の男だ。ぼーっとした、冴えない顔をしていて、間者だとも思えない。髪を背中でいい加減に束ねている。 「あ、リーナ様、お久しぶりです」 「……お前、誰だ」 リーナが言うと、男は大げさにのけぞった。 「やっぱり、気づいてもらえなかったですねえ。私ですよ、扇職人のグレンノルト=イーズです」 「ああ、お前か。そういやそんな細い目の奴、お前しかいないな。ひげをそったりするからだ。……で、何をしに来たんだ? お前、シェーナにいた筈じゃなかったのか」 「そうなんですよ、それでプーツァにリーナ様が来るっていうんで、情報を進呈しに」 「何だ。手短に言え。からかったりしたら斬るぞ」 「まじめな情報ですって。……今回のエルーブの動きに同調して、何やらしようとしている奴等がいるんで」 「ほーう、奴等のやりそうなことだな」 「漁夫の利をねらってるんでさ。で、反対派ともめてまして……。どうしますか、何だったら、ジャマな人間を一、二人、動けないようにしますか?」 「いらん。そういうことはヌーグ様に直接言ってくれ。……が、せっかくここまで来たんなら、ちょっと頼みたいことがある」 何やら耳打ちする。グレンノルトは頷いたが、去り際に余計な一言をぼそっと呟いた。 「ヌーグ様と一緒になれば、ますます、面白いことになるのに……」 「──とっとと行けっ!」 その日は、何事もなく過ぎた。 「夜襲をかけてくるのではないかと思ったんですが……」 ニーゼが自信なさげに言う。 「普通は、そうするわね。何を企んでいるのかしら」 ミラは首を傾げる。 「どうあっても、あの陣を襲わせたいということかね」 シャフイはリーナを見上げる。 「攻める」 リーナは短く言った。シヤフイは目を見張った。 「必ず罠がありますぞ」 「あったらあったで食い破るまで。いにしえの兵法にいう、十なればこれを囲み、五なればこれを攻め、倍すれば分かち、敵すれば戦い、少なければ守り、若かざればこれを避く、と。数はこちらがあちらの五倍だ。兵糧の減り方もこちらの方が早い。あと三、四日のうちに決着をつけ、プーツァに入らなければ。どちらかといえば、これは時間との戦いだ」 まともに戦っても勝てないことは、最初から分かっている。 に、しても──この圧倒的な戦力差は。 (一人一人の能力は、互角のはず……なのに) エリオットは、崩れ立つ味方を見て呆然とした。 (所詮、にわか仕込みの兵では、歴戦のキーサ軍には……) 「エリオット、何を惚けている! 撤退するぞ!」 耳元でヴァルの声が聞こえ、はっとして剣を握りなおす。 「撤退! 撤退!」 自らも叫びながら味方の援護に回る。剣を合わせる、その敵の一人一人の強さに驚く。 (まさか、これはキーサの最精鋭部隊?) 兵たちのための囮になってやる。逃げる時間をつくってやるための。その時間を稼ぐ間、防ぐのが精一杯だ。自分は元々、従姉とは違って武芸は達人の域にまでは達していないが。 「お前はエルーブの将かっ?」 まだ若い、少女といえるほどの女の声がした。剣を合わせていた敵兵たちがさっと退く。 「私はキーサの第二王女にして外兵尉丞ミラ。剣聖ラムトゥナ様仕込みのこの剣、受けるがよい!」 「エルーブ邑兵尉丞、エリオット=クェル!」 昨夜、ヴァルから計画の全てを聞いていたのが災いした。軍司を捕らえられなくとも、この王女を──と、思ってしまったのだ。 「いざ、尋常に勝負……っ」 ほんの十合ほどだった。勝負はあっけなくついた。この少女は、この地に来たキーサ軍で、おそらく最も悪い相手であったのだ。 「邑兵尉丞、って言ったわよね。すると、今度のエルーブの動きについて、ぜーんぶ知ってる訳よね? 敵将の名は何て言うの? どういう人? ね、教えて」 エリオットは口をつぐんでいる。 「来てるエルーブ軍の数はどのくらい? まさか、あれだけってことはないわよねー。他の部隊は、どこに潜んでるの? 夜襲の予定は? 今日? そうよねー、まさか黙って引き返すはずはないわよね、あれだけハデに挑発したんだもの」 ふん、と横を向く彼の顔を見やって、ミラはにやにやと笑う。 「けっこうあんた、いい男ね。歳はいくつ? はたち前でしょ」 「一九だ」 「ふーん、そういうことは答えるんだ。ロの堅さ、結構わたし好みよ」 「王女、捕虜をからかうのはやめなさい」 たしなめ、リーナはエリオットの正面の椅子に腰かけた。 「敵の副将らしいな。何も話す気はないか」 「……」 「それとも、よほど将を信頼しているか、だな。すぐに身柄を取り返しに来る、という」 リーナは立ち上がった。 「まあ、今晩の夜襲ぐらいは予測済みだ。どの程度のものか、見せてもらおうじゃないか」 夕やみが空を藍色に染め、兵たちが食事を済ませてくつろぎ始めた頃、山ぎわの方から敵兵が侵入し、辺りの明かりを切り倒して回った。キーサ兵たちは取り押さえようとしたが、人数自体少なかったらしく、結局捕り逃した。 「捕虜は?」 「いるわ」 ミラが答える。すると、この夜襲は捕虜奪回を狙ったものではないのか。 場所を移し、人払いをする。 「おそらく、『二重夜戦の計』だろうとは思うのだが」 「それにしても、あざとすぎますね」 「一応、誘いに乗ってやろうとは思う。副将も返してやろう。だが、その後、何を狙っているのか……」 「これは推測なのだが……」 シャフイが、ぽつりと言った。 「もし、次の夜襲が真夜中であったら……」 ヴァルは、計画の狂いに少々苛立っていた。 計画では、もう少し人数がいる予定だったから、初戦での犠牲は痛い。エリオットが捕らわれたのも予想外だった。残存兵力は……八〇くらいか。 「まあ、これだけいれば何とかなるだろう」 と、昨晩と同じことを言っている。虚勢ではなかった。計画のおおもとは崩れてはいないのだ。初戦はわざと敗走した。夜襲一回目は少数で敵陣を攪乱させ、すぐに退いた。 「問題は、次でどれだけ残るか、だが……」 不安そうな兵の目が痛い。自分は必ず勝つと確信していても、兵がそうであるとは限らない。だから、次の夜襲の時には、完璧に勝たねばならない。もともと夜襲の勝敗は数ではないのだ。 キーサの陣には煌々と明かりが点っている。当然、おびき出しの為の策だ。まわりに兵が伏せてあるにちがいない。 「中に入ったとたん明かりが消える、そして伏兵が襲いかかってくる、そういう策に違いない。それを逆手にとるのだ。明かりが消えれば敷か味方かの区別がつきにくくなる。すると、同士打ちをおそれるキーサ軍は思うように戦えまい。お前たちは、外へ外へと斬り進めばいいのだ。外へ出たらこの場所へ集結しろ」 兵たちには、こういう指示を与えておいた。……私は天才だ。歴戦の将リーナの策ですらこうやって逆手に取ることができる。 やはり陣はもぬけの空だった。中へ中へと、一丸となって進んでいく。こちらはできるだけ固まっていた方がいい。下手に散っていると、同士打ちの原因になる。 椅子に、エリオットが縛りつけられていた。目隠しと猿ぐつわがかまされている。ほどいてやると、エリオットは叫んだ。 「邑兵尉、これは罠です!」 そのとたん、明かりが倍以上に増えた。昼間のような明るさに包まれる。 「そこかっ、敵の大将!」 少女の声がした。はっと気づいたエリオットが口を押さえたときにはもう遅い。キーサ軍の全軍が、十重二十重に本陣を取り囲んでいた。手に手に松明を掲げている。 「投了、だな。エルーブの邑兵尉よ」 ひときわ目立つ緑の鎧を着た女将が言う。 「……私は、まだ負けたわけではない」 ヴァルは呟いた。その表情は自分の才能への自信に満ち溢れていた。そしてもう一度、今度はもっとはっきりと言った。 「私は、まだ負けてはいない! 私に、あと百の兵力があれば……」 「そう、私はお前に勝ってはいないな」 リーナは頷いた。 「私がお前に勝ったのではない、キーサの軍司がエルーブの邑兵尉に勝ったのだ。エルーブの邑兵尉であること、それが今のお前の限界なのだから。あと百、と言ったが、私にあと百の兵力があれば、たぶん初戦であの陣を壊滅させていた。お前の敗因を教えてやろう。考えすぎることだよ。机上の空論にこだわらなければ、もっとよく戦えただろうに。さあ、もういいだろう。剣を捨てて投降したまえ」 「誰が、投降などするか」 ヴァルは吐き捨てた。そんな気はさらさらなかった。リーナの話も聞いてはいない。ひたすら隙を窺っている。 「まだ若いんだし、命を惜しめば良かろうになあ」 シャフイが呟く。その瞬間、ヴァルは剣を抜いた。背後の敵に切りつける。エリオットも、ヴァルの兵たちも、そしてキーサ兵たちも、呆気にとられて止める気にもならない。ヴァルは剣をかざしたまま陣の入口ヘむかい、外へ出ようとした。 「待った!」 前方から来る一隊の兵。そして、その先頭に立つのは、 「御用だよ、ヴァル」 エルーブ募兵尉、エリーノ=クェルであった。 こうしてプーツァの乱──別名「夜襲戦争」は、幕を閉じた。 |
アミエル=ムウサ──という名の女が、今は唯一の手がかりだった。その名に何ら愛着を感じているわけではない。しかし、今はあれを殺させるわけにはいかないのだ。 姉を捜すためだけに、「私」は生きてきた。その唯一の手がかりを見失ったら、こいつは絶望して死ぬかも知れない。 「私」が死ねば、私も死ぬ。私が「エルリーク」の全人格を乗っ取ることも不可能ではないが、それではどのみち生きてゆけない。私は暗殺の腕なら誰にもひけは取らぬ。だがそれ以外のことは何もできないのだ。「エルリーク」が人として生きてこれたのは、こいつが居てくれたおかげだ。 「どうしたの? どうして、応えてくれないの?」 不安げに、「私」が問いかけてくる。 「……少し、考え事をしていた」 「難しいの?」 「作戦は、『双剣』『双身』に任せてある」 「じゃあ、何を考えてたの」 「……」 「ぼくには、話せないことなんだね」 「……いや」 こいつを、死なせるわけにはいかない。死にたくない。 「お前を守ることを、考えていた」 そのために、私は生まれた。七歳の時から、ずっと。 「……ありがとう」 そう、答えて……エルリークは限りについた。 「決行は今晩だ」 暗殺組織「三振り太刀」の『名剣』クラス三名が、カノールのとある宿屋の一室に顔を揃えていた。 一人は両目に眼帯をつけ、目玉の刺錬を施した悪趣味な服をまとっている。『双剣』のコンラード、『双剣雪柳』を佩き『無音十字剣』を使う。 「私は手伝うだけだ。手筈は整っているんだろうな」 『双貌』のクレン・エルリーク。かつてそう呼ばれた銀髪の青年は、今は暗い瞳をして寐の前にうずくまっている。 「さー、わたしは知りません。今回の件は全部『双剣』に任せてありますから」 道士服を着た若い女は笑っている。『双身』のラーシャ、というのが彼女の名だ。とぼけた性格だが、それが彼女の本質を示すものでないことは、『三振り太刀』の者なら誰でも知っている。 コンラードは唇の端で残虐な笑みを浮かべた。 「現在、軍司リーナ=トゥラはプーツァに戦後処理に向かっていて留守だが、明日か明後日には帰ってくることになっている。軍司配下の兵のうち精鋭千はプーツァ城に駐屯中だ。つまり今の王城を守っているのは城司配下の衛兵とあとはスカばかり、ということだ。守備の兵の気が緩んでいる隙を衝いて城に潜入する。そこからは別行動になるから、この見取り図を良く見ておけ。おれは右のこの扉から侵入し、衛兵を減らしておく。見つかったら引きつける。『双身』は左の厩舎の方で火事を起こせ。なるべく派手にな。『双貌』……貴様には正面からこっそり侵入し、王宰の首をあげる役をやる。貴様は見つかるな。風のように侵入し、見つからずに出てこい。二刻後までに戻ってこなければ失敗したものとみなす。いいな」 久しぶりにカノールに帰ってきたグレンノルト=イーズは、街を歩いていて、ひとりの人官が刀研屋と話しているのを聞いた。どうやら袖の下として名剣ダークブレイドというのを受け取ったらしい。……ヌーグ様にご報告しなければ。男が路地に入ったところで針で気絶させる。その体を肩に担いで、グレンは城へと向かった。裏門の側扉の鍵を開けようとしたが、手ごたえがない。 「閉め忘れですね、不用心な。これもご報告しなければ」 内側から鍵をかける。夜も遅い。ひょっとすると、ヌーグはすでに眠っているかもしれなかった。 「不審な奴だと思ったら、お前か」 よく通る女性の声がした。軍司リーナ=トゥラだ。 歩き出しながら、リーナはグレンの肩を見て不審げに眉をひそめた。事情を説明すると、その眉はさらに寄った。 「成程。そのような不正がまかり通っているとあっては、放っておくわけにはいかぬな。王国の威が下がる。私の領分ではないが」 そんな話をしているうちに室に着いた。衛兵が軍司に礼をして扉を開ける。王宰ヌーグ=シャルは政務を終え、茶を飲んですっかりくつろいでいた。服も正服ではなく、一般民が着るようなゆったりとした寝衣だ。 「グレンにリーナか。二人が連れだってとは珍しいな。まあ、入れ。それにしても久しいな、二人とも」 「軍司殿もいまお着きですか」 「到着は明日の予定だったと思うが?」 リーナに茶をすすめながらヌーグは扇を手に取った。リーナは頷いた。 「幸いにも順天が続き、通常行の一日半余りも早く到着しました。まあ多少、馬に無理はさせましたが」 「貴女も無理をしたんだろう。到着の挨拶など、夜が明けてからでいいのに」 「お気遣い、感謝します。しかしこれくらいで倒れるほどやわな身体は持ち合わせておりませんので、ご心配なく」 「まあ茶でも飲んで、ゆっくり寝め。疲れていないはずはないんだから。貴女はこの二節というもの、家に帰っていないじゃないか。親孝行はするものだぞ、軍司」 「ところでヌーグ様、グレンの肩が重そうなのでそちらの議を先に聞いては如何ですか」 リーナは話をそらせた。グレンは大まじめな顔をして呟いた。 「ヌーグ様、軍司殿といっしょになってみては? そうすれば、少しは、おしとやかになると思うんですがねえ……」 「お前はやり手ババアか。私を見るといつもそれだな」 リーナは睨みつけた。グレンは聞かなかったふりをして男を床に下ろす。 「実は、この男がこんな事を言ってましたんで」 「なるほど、そんなことがあったのか」 ヌーグはグレンノルトの頭をぱたぱたと扇いだ。 「ご苦労。まあいかに王宰といえど、末端まで目を光らせるのは無理だからな。吏を全部調べようとは思わないが、見せしめくらいにはなるだろう──」 と言いかけたところで、慌ただしく扉を叩く音がした。扉を開けると、衛兵のひとりが転がり込んできた。王城内で火事が発生した、という。しかも、 「場所は厩舎でして、火の気などまるでありません。燃えるものなら大量にありますが……」 「つまり、放火か」 「侵入者の可能性もありますね」 リーナが眉をしかめた。 「我々の注意をそちらに引きつけて、別の目的を遂行するというわけか。よくある策ではあるな」 誰だ、放火なぞした不届き者は。 城司ヴィシュ=ディノはきわめて不機嫌であった。昼中気を張っていた。副官に後を任せてやっと眠れたと思ったら、一刻もせぬ内にたたき起こされたのである。 東階段を駆け下り、そこいら辺にいる衛兵たちをあるいは伝令に走らせ、あるいは後ろに従えて現場に向かおうとする。一階の最も東の扉、そこに降りていこうとして、足を止める。 「城司殿……?」 怪訝そうに言う衛兵の手から炬をとりあげ、さしだすと、その灯火の中に一人の男が現れた。 「成程、貴様が城司か。あまりにも手ごたえがなくて失望していたところだ。これで少しは楽しめるか──」 男の足下には扉の外と中を守っていた衛兵たちの無惨な死体が転がっている。それに気付いた衛兵たちが、手に手に得物を持って撃ちかかるが、まばたき一つの間に五人が薙ぎ倒された。 「……お前は何者だ。何の目的があってここに侵入した」 抜剣しながら、城司は尋ねる。悪趣味な服は、この男の身分を堆し量る材料とはならない。 「死にゆく者への手向けだ。特別に教えてやろう。暗殺組織『三振り太刀』のコンラード。あの世で死神に会ったらそう言いな」 「暗殺者……王宰殿の首が望みか」 ヴィシュはぎり、と唇を噛んだ。その彼の前で双剣が鳴る。 「そんなことはさせぬ。我が名は『謀剣』のヴィシュ=ディノ。王国への忠と軍司への約にかけて、ここは通さぬ……!」 「ただの火事だったのかな」 ヌーグは肩ごしに外をのぞいた。奥の赤はもう見えない。 「厩舎から自然に火の手が上がるはずがないでしょう!」 リーナはヌーグを睨みつけた。 「混乱を誘ってその間にやることといったら暗殺しかないじゃないですか。一番狙われるのはヌーグ様、あなたですよ! 自覚はあるのですか !?」 「……その通りだな」 応えたのはヌーグではなかった。リーナは振り返った。銀の髪に青紫色の瞳をした青年は肉食獣の笑みを浮かべた。 「いかにも、我が目的はそこの男の首だ」 「やれやれ、迷惑なことだな」 ヌーグは呑気そうに言って扇をあおがせた。 「貴方に恨みを買うようなことでもしたかな。覚えがないが」 「恨みなどない。大義のために、などと言うつもりもない。ただ、貴様の首が必要なだけだ。理由としては充分だろう」 「物騒な話だな。人の首なんて、持ってたって仕方なかろうに」 「ほざけ!」 エルリークは剣を抜いた。 「秘剣……影身……!」 青年の姿が何重にもダブって見える。リーナは青年とヌーグの間に立ちふさがろうとする。その腕を、グレンが掴んだ。 「何をする!」 「絶影……」 音もなく剣先が伸び、ヌーグへ向けて迫る。ヌーグはあまり素早い方ではない。武術も人並みだ。いかなる達人も要人も凡人も、確実に屠ってきたこの必殺の剣を避けられる筈もなかった。ましてや剣は妖刀燕飛だ。エルリークは成功を確信していた。 ヌーグの身体に剣が触れたと見えたその時、ぱし──と、何かにひびが入るような音が空気を割った。目に見えない壁が形成される。弾き飛ばされた刀は壁にぶつかり、刃先は粉々に砕け散った。刀の柄を掴んでいたエルリークも強く背を打った。 リーナは倒れたエルリークを見、ヌーグを見た。手に掲げた扇……その羽根は一本一本が雷に撃たれたように毛羽立ち、埋め込まれた水晶の球は透明な光を発している。 「ヌーグ様……」 「しばらくは近づかない方がいいぞ、軍司。しびれるから」 「扇が……?」 問いではなく、確認だった。ヌーグは大きくあくびをした。 「もう寝るよ。夜も遅いしな。リーナ、後始末は頼む」 「……あの……暗殺者は一人とは限らないと思いますが……」 「分かっただろう? グレンの扇がある限り、このヌーグを害することは誰にもできないんだ」 カノール王城内に暗殺者が侵入した、との報を受けてシィル=アーレインはほくそ笑んだ。王宰ヌーグ=シャルは命を拾ったらしい。彼にしてみればどちらでもよかった。どうせ暗殺などという始息な手を使うのは反キーサ王国連合に決まっている。これで奴らの評判が堕ちればしめたもの、敵の敵は味方ということでキーサと和を結ぶことも容易になる。ヌーグ=シャルが死んでいればプーツァを奪い取ったところだろうが、これは想像の範疇に属することだ。 「王宰殿、エルーブの水吏長殿をお連れしました」 「ご苦労様。……って、城司か。無理はするなと言ったろうに」 椅子に腰かけた男は、ぱたぱたと扇であおぎながら声をかけた。ヴィシュは一礼した。 「無理などしてはおりません。十分に休息はいただきました」 「嘘をつけ。軍司といい城司といい、どうしてこう軍の奴らは仕事熱心かなあ。──まあ、いい。お前は退がって休んでいろ」 「は……」 「で、エルーブ水吏長殿。御用の向きは?」 気安く尋ねてくる。目の前の男はたしかに噂に名高いヌーグ=シャルであるはずだが、いかにも策士然とした人物を想像していただけに、飄然としたようすには違和感をおぼえた。 「プーツァの件の事後処理について、公式に議を持った方がいいと思いまして」 「そうだな。エルーブはどうするつもりだ?」 「キーサに対しては謝罪はしません。物的な賠償もしません」 シィルはヌーグの表情を窺ったが、扇に隠れてよく見えない。 「ほう」 「キーサに救援を求めたのはあくまでプーツァであって、我々はキーサと戦うつもりなどありませんでした。キーサが手間をかけ資金もかけていることは知っていますが、それはプーツァを通して受けてください。それより他に渡しはしません」 筋道は通っているようだが、実のところ、全くの詭弁である。プーツァには渡すというのは要するにプーツァは一邑、エルーブも一邑、キーサも一つの邑としてみなす、ということである。 ヌーグは笑った。 「話はそれで終わりか?」 「そうですね」 「そうか、じゃ気をつけて帰ってくれ。こんな城の中にまで暗殺者が入ってくるような、物騒な世の中だからなあ」 冗談とも本気ともつかない。そうですね、と口の中で呟いて、シィルは部屋から退出した。 その数日後、キーサ王国は反キーサ王国連合に対して宣戦を布告し、エルリークはキーサの募兵に加わることになった。 暗殺組織『三振り太刀』の内部の情報と、姉についての情報を引き換えることを条件に。 |
「ヌーグが重態だって?」 独立暦四〇一年人の月のカノールは、この情報から始まった。 「暗殺者が入ったと聞いたが、もしやその傷が元で……?」 などという憶測が飛び交っていたが、事実はキーサ王城の厚い城壁に阻まれ、杳としてわからない。 プーツァに行き、エルーブとプーツァの交渉の行方を監視するよう命ぜられていた軍司リーナ=トゥラは、その報を聞いてすぐに馳せ戻ってきたが、ヌーグの私室から出てきたときの真っ青な顔を見れば、どんな様子だったのかが容易に想像できる。 順風満帆であったキーサ王国に、にわかにまきおこった暗雲。民たちも祭りをひかえ、大通りも人通りが少なくなるなど、王都カノールは季節はずれの冬を迎えたようであった。 これを聞いて驚喜したのはむろん、反キーサ王国連合である。前回はシェーナを見殺しにした形となった諸邑も、 「先陣を切るのは我が邑!」 と、勇んで兵装をととのえていた。 エルーブでもただちに議が召集された。 「どう思いますか、水吏長殿」 邑宰の問いに、皆の期待の目が集中する。 「私が会ったときには、そんな様子は微塵もみえませんでした」 シィル=アーレインは、思った通りを答えた。空気が動いた。わずかな失望の空気だ。 「負傷した様子もありませんでしたから、私には噂はにわかには信じられませんが」 「しかし、間違いない情報です」 外吏長が胸を張った。 「カノールヘ派遣したどの間からも、同じ事を言ってきています。カノール城内はまるで喪に服しているようだ、と。街のどこを見ても、笑い騒ぐ者はなく、大道から人の半分が消えた、と」 しかし、シィルにはあの飄然とした男が病に倒れるとはとても想像できなかった。まあ、人間である以上、あり得なくはないと思うが…… 「で、これが一番重大な問題なのですが」 邑宰がためらいがちに言った。 「キーサ王宰が重態であるときいて、反キーサ王国連合が動き出しています。反キーサ王国連合と我が邑とは宿敵──しかし、連合がカノールを手に入れれば、強大な力となり、我が邑に害をなしましょう。それよりは連合と手を組み、利の一部を得るべきである、と私に進言してきた謀もいるのですが」 庫吏長が大きく頷いた。 「ヌーグ亡きキーサなど、連合の力をもってすればひとたまりもないでしょう。すると、我らの運命はそれこそ風前の灯火となります。フィーブの援助を得ているとはいえ、南方の邑の建設に巨額を投じている現在、連合と戦うだけの資金はありません」 「しかし、それは連合が一つにまとまった場合……ですな」 兵吏長が笑った。 「連合が一つにまとまったことなど、いまだかつてありましたか。たとえキーサを倒したとしても、すぐに内紛を起こすのは必至。そんな中に加わることなどありません。我々は今は傍観し、降りかかる火の粉を払うことこそ肝要と思いますが」 「兵吏長の意見に同感です」 シィルは言った。 「私の妄想かもしれませんが、私にはどうしてもあの男が病気とは思えないのです。反キーサ連合のはしゃぎぶりを見てほくそ笑んでいるような気がしてならない」 「では、貴公はあれは仮病だと申すのか」 「可能性としては考えられると思います。私ならそうしますから」 反キーサ王国連合軍はアーヴ周辺の平野に終結した。その数は約二万五千。シェーナ、アーレ、ディンといった大邑をはじめとした諸邑の外兵を集めた数だ。 情報を聞いて、リーナは激怒した。 「こちらの足元を見て攻めかかるとは──何て恥を知らぬ連中だ! 名将名宰を尊ぶとか、そういった心は奴らにはないのか!」 「あるわけがないじゃない」 ミラ=シャルははきすてた。 「そういう連中だからこそ、まだ私たちに一度も勝てないのよ」 「しかし、王女……っ!」 リーナは血を吐くようなため息をついた。 「私は……私は、耐えられません。王宰殿を失ったら……我が国は、キーサは…それを想像すると……」 泣き出さんばかりの表情をしている。さすがに、衆目の前で涙を見せることはないが。 「私、正直に言うと、満足に戦える自信がありません。普段の私なら、十倍の兵馬でも破ると言えますけど、今は……私は……」 「しっかりしろ、軍司」 すっかり傷の癒えた城司が、肩を叩いた。 「城司……」 「軍司が弱音を吐いてどうする。王宰殿もお嘆きになるぞ。……心配するな。カノールはしっかりと守ってみせるから」 「……そうだな、城司」 リーナは笑みをつくったが、かなり無理のある笑みだった。くるりと鍾をかえして、廊下を去ってゆく。 「……いいのか、針師」 いつの間にか来ていたグレンノルト=イーズを振り返って、城司は困惑げな顔をした。 「あれでは、軍司が哀れではないか。それに、大丈夫なのかと街を歩けば民に問われ、家に帰れば家族に問われる。私も城守の総監である以上、知らぬとは言えぬし…‥もう、限界だぞ」 「同感よ」 ミラ王女も大きく頷いた。 「軍司もだけど、内廷から出られなくて弟にも会えない王の気持ちも考えてよ。私だっていつ喋っちゃうかわからないわ」 「あと数日の辛抱ですよ」 グレンは笑った。 「私はこれから、反キーサ王国連合の方に行ってちょっと細工をしてきます。ああそう、出立は明朝にしてくれと、ヌーグ様から伝言がありましたので、リーナ様に伝えて下さい」 翌朝、キーサ軍一万五千がアーヴに向けて出発した。七年前と同じ道のりだが、今回は皆一様に足が重い。このまま帰れなくなるのではないか──いや、帰るべき場所が失われてしまうのではないか。そういったおそれは、ロにはしないものの誰もが抱いているのだった。 リーナは振り返った。後ろ髪が引かれて仕方なかった。せめてもう一度、顔を見てから出たかった。それがよけい、不安をかきたてるものだとしても。 (ヌーグ様……) 振り切るように馬に鞭をあてる、その音が胸に空しく響く。 かくして両軍は、アーヴの野にて対峙した。 「やあ、我こそはシェーナ兵吏長ガードン・トゥラ──」 おそらくは熾烈な順番争いの末に一番を勝ち取ったのだろう。胸を張って言いかけたが、リーナの声がそれを中断させた。 「よくもしゃあしゃあと私の前に顔を出せたものだな、兄上」 その声は低く、怒りの念で大気もふるえるようだ。みな沈黙した。その静けさを割って、リーナの弾劾が続く。 「哀しみにつけこんで、邑を侵略しようとする貴様らのやり口、人とも思えぬ! よくも……よくも、我らが心を踏みにじってくれたものだな。天が地が許しても、私は貴様らを絶対に許さん! 絶対に !!」 鬼気迫る、とはこのことだった。つねに口上は感情的なリーナであったが、これほどに苛烈なものは今までなかった。キーサ軍は、そして今まで浮ついた気分でいた連合軍も、水を打ったようにしいんと静まり返った。 「取り込み中のところ、悪いんだが……」 リーナの脇に控えていた騎馬が、すっと馬を寄せた。リーナはきっ、と睨みつけたが、一瞬後には目を見開いたまま凍りついてしまった。 ヌーグ、だった。 普段の正服ではなく、鎧甲姿であった。左手で手綱を引き、右手に外した甲を抱えている。だから誰にも気づかれなかったのだ。 「さて皆さん、このたぴはこのヌーグのためにわざわざお集まりいただいたようで、恐縮なことだ。改めて礼を言おう」 いつもの飄々とした口調ではない。重々しく、ドスを効かせた──あからさまに芝居がかった喋り方をしている。だが、その声はまちがいなくヌーグその人のもので、後背に控えるキーサ軍、対峙する連合軍、どちらにもどよめきが広がった。 「反キーサ王国連合軍の諸君。諸君らの私に対する考え、よく見せてもらった。そして、人の不幸につけこんで勝利を掠めようという卑しい心根も、とっくりと見せてもらった。そういうことだから、今日は自分たちの愚かさと無力さを、じっくりとその身をもって味わってくれたまえ」 また、しいんと辞まりかえる。あまりの衝撃に、反論する者は一人としていなかった。 「そして、我がキーサ王国の者たちよ」 向き直る。兵たちは誰が命じたわけでもなく、いっせいに左手を胸にあてて礼をとった。 「 ヌーグは従兵から旗を受け取った。緑の地に金糸で縫い取られた×の字。一本の線が武を、一本が文の道をあらわし、両道紋と称す。キーサ王家のもととなったシャル族族長家の頃から約七百年の間、受け継がれてきたキーサの紋だ。 「今日ここに、改めてキーサ王国の発展を誓う。この旗とともに、誇りある歴史とともに。このアーヴの地で、ふたたぴ輝かしい勝利を得んことを。諸君の奮戦を期待する」 「────行くぞ!」 リーナが大声で叫んだ。それとともに、キーサの全兵が、いっせいに突撃を開姶する。兵数は三対五……しかしそんなものはすでに問題でなかった。勝敗は戦う前から決していた。 エルリークは戦いの後、外兵長に呼び出された。彼は暗殺の技を用いて、シェーナ邑宰とアーレ兵吏長、二人の将の首をとった。戦功の賞だろうと思った。 「それもあるのだが」 外兵長は一通の書簡を渡した。 「ヌーグ様から賜ったものだ。読むといい」 訝みながら、書簡を一枚一枚ひらいていく。 ──信じられなかった。 「クレン・エシリル……という者が、今、イリス王国の神兵尉・募兵尉の丞として働いている……」 ヌーグは約束を守ってくれたのだ。エルリークが知っている『三振り太刀』の情報は二年も前のもので、しかも自分はヌーグを暗殺しようとした者だ。破談になっても仕方なかった。 イリスに行けば、姉に会えるのか。 イリスに行きさえすれば…… !! 「ふう、ようやく城の中を自由に出歩けるな。一室の中にこもるってのは本当に窮屈だったからな」 「それを余人の前で言ったら、殺されますよ」 グレンは笑った。 「特に誰かさんなどは」 「それなんだ。困っているんだが。……あの戦い以来、ひとことも口をきいてくれなくてな……」 リーナの戦いぶりはいつにも増して凄まじかった。ミラ王女の証言によると、「一人で千人は斬ったわ」という。それは誇張としても、ほとんど自分の身も省みずに斬りまくっていたことは確かだ。陣に帰ってきた時には、人馬ともに全身鮮血にまみれ、元の色が残っているところはなかった。血は返り血だけではなかった。筋が切れるのではないかというほどの深傷をいくつも負っていた。が、何よりも彼女を傷つけたのは刀剣槍戟ではなかった。 「だから軍司を騙すのはやめようと言ったんだ。まったく、いつになったら機嫌を直してくれることやら……」 「直してさしあげればいいではありませんか」 「簡単に言うな。あれの頑固さは七年間で身に沁みてるんだ……」 扇をあおぐ手が止まりがちになる。それを見て、グレンはにやりと笑った。 「リーナ様に、自分の気持ちを正直に出させてあげればいいんですよ。簡単なことです」 「軍司は、いつも感情的な奴だが?」 「いっしょになると、ひとこと言ってあげればいいんです」 「……お前、軍司のことになるといつもそれだな」 ヌーグは沈黙した。静かに頬に風を当てる。 「……とにかく、見舞いに行ってくるか。まだ安静のはずなのに、ひょいひょい出歩いてるがな……」 「行ってらっしやい。健闘を祈ります」 「──何の健闘だ」 ヌーグは不機嫌そうに言ったが、ふと扇を落とした。きまり悪そうに拾い上げてまた歩き出すヌーグの背を見て、グレンは一言、「おめでとうございます」とつぶやいた。 コツコツ、と扉が叩かれるより前に、リーナには誰が来たのか分かっていた。だが出る気にはなれなかった。 「……入っていいか」 返事はない。 「勝手に入るぞ」 リーナは椅子に深く身を沈ませ、ぼんやりと宙の一点を眺めていた。服は正服だが、左腕を吊っているのが痛々しい。 「軍司……悪かったと思ってる」 「……」 「済まなかった」 「……」 返事がない。 「軍司──」 「聞こえてますよ、王宰殿。それで、どうしたというんですか」 ……相当、怒ってる。 ヌーグはここに来たことを少し後悔した。 「貴女を騙したことは謝る。貴女を、策のネタにしたことは……」 「それは、構いません。そのための部下ですから。……でも」 リーナはがばと立ち上がった。右の手でヌーグの頬を殴りつけようとし──寸前で気づいて止める。激情に駆られるまま、言葉を叩きつけた。 「あれも芝居だったんですか !? あんなに苦しそうだったのに。本当に……本当に、死んでしまうかと思ったのに……っ」 「……軍司が、見舞いに来てくれた時のことか……」 軍司がプーツァから駆け戻ったと聞いて、ヌーグは本当に重病人を演じることにした。グレンノルト=イーズの針の力を借り、少々化粧も施して、顔色の悪さ、頬のやつれ、荒い息、かすれた声、脂汗……等々を演出したのだ。芝居は完璧だった。 「分かってます。策に必要だったってことは。でも……でも」 リーナは椅子に倒れこむように座った。 「失うと思った……すべてを失うと……耐えきれない、と。私は全然、疑わなかった……ただ、失うと思うと……怖くて…」 リーナの瞳が濡れている。初めて見る表情だった。拗ねたように唇を曲げて、こみあげるものに耐えている。 「……城司も王女も知っていたのに、私は知らされなかった……私はヌーグ様に一番近いつもりでいたのに……私だけが追いつめられて…ずっと、騙されてた……」 「悪かったと、思ってる」 「ヌーグ様を責めてるんじゃ、ありません」 リーナは俯いた。握りしめた拳の上に、ぽたり、ぽたりと滴が落ちる。 「ただ、悔しいだけ。信じきってた自分と、踊らされてた自分と、失うのが怖いと、気づかされてしまった自分と──それから」 自嘲。 「それを、とうとうヌーグ様にぶつけてしまった。……言ってしまうんじゃないかって思ってた……だから、口もきかないって、そう決めてたのに。自分が悔しい……泣きたくなんて、ないのに…」 「……リーナ」 ヌーグは扇を置いた。 「お前だから……だったんだ。お前だから、知らせなかった。お前だから、欺いた。お前でなければならなかった。俺を失って、一番哀しんでくれるのは、お前だから……」 「……ヌーグ様?」 「苦しませて済まなかった。……お前はいつも、俺のことを一番に考えてくれる。分かってた。お前が、こんなに苦しむことは。分かってて、それでもやった……それが、俺だ。だから、誰の想いにも応えてやれないと思ってた……」 椅子越しに、そっと抱きしめてやる。身体のあちこちが痛かったが、それよりも人の気につつまれる感触がここちよかった。 「七年間ずっと、お前は俺の支えになってくれた。これからも、ずっと側にいてくれるか?」 「……! それって……」 「そうだ」 ヌーグは優しく頷いた。リーナはふと気づいて睨みつけた。 「これも、芝居じゃないでしょうね?」 「これが、本当の俺だ。……信じてくれないのか?」 「信じるわよ……ずっと、信じてきたんだから」 「アーヴでのリーナの言葉……嬉しかったぞ」 リーナは気づいた。ヌーグが自分のことを「俺」と言うのも、「お前」と呼ばれるのも、「リーナ」と名前で呼んでくれるのも、ぜんぶ初めてのことだ。 この人は、今までずっと、自分を隠していたんだろうか。あの、白い扇のかげに。王宰という位のため、キーサという国のために、自分を殺していたのだろうか? ──でも、私は確かに、この人のために生きてきた。他の誰でもない、この人のために。 「私、ずっとあなたの側にいるわ。あなたと一緒に、この国を守っていく……これまでと同じだけど。同じように、ずっと……」 命、尽きるまで。ずっと、戦っていく…… |
| ■ 前のページに戻る |